鹿足郡薬剤師会 平成25年12月研修会資料
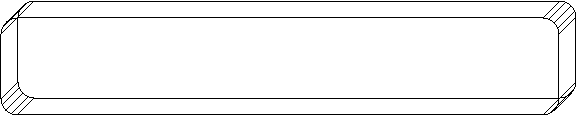 妊婦と授乳に関する薬学的管理
妊婦と授乳に関する薬学的管理
「対応基本手引き(改訂2 版)2012 年12 月改訂」その他より

【 妊娠の時の薬剤 】
◯カゼ•喘息
1) かぜ症候群の予防
・患者さんより 「 ヨード含嗽薬を用いてうがいを毎日行っている。」
≪ 問題点はあるか ≫
・ヨードは胎盤を容易に通過し、胎児が甲状腺中毒になることがある
≪どのように改善すればよいか≫
•水でのうがいを励行することで、かぜの感染が減少することが無作為化比較試験でわかっている
•呼吸器系ウイルス感染の拡大を防止するためには、 特に手洗い、マスクの着用が有用であることがわかっている。
2)発熱のあるとき
≪妊婦に解熱剤どの解熱剤を勧めるか ≫
•妊娠中の女性に使用する解熱鎮痛薬としては、「アセ アミノフェン」が選択される。
≪アセトアミノフェンが危険なのか安全なのか ≫
•「アセトアミノフェン」は、胎盤を通過する。
•長期大量投与では、母体の肝障害・腎障害、新生児の腎障害の報告もあるが、通常量の短期使用では、安全であることが知られている。
・ラットの動物実験では、「弱い胎仔の動脈管収縮」がありが、動脈管の内径が半分になるED50は、300mg/kg と臨床量からほど遠い量である。
≪妊婦に使ってはいけない解熱剤はなにか)≫
•妊娠後期は、「NSAIDs(プロスタグンディン合成を阻害するタイプ)」が禁忌
≪使ってはいけない理由はなにか≫
•「胎児の動脈管を収縮する可能性がある」ので使用禁忌になっている。痛みの症状が強い場合でも頓用、つまり最小限の投与にすることが必要であ
※「動脈管」とは、胎児が肺を使わない呼吸をするために必要な器官だが、出生と同時に閉じていき、肺呼吸へ移っていく。プロスタグランディンがこの動脈管を開存させているため、プロスタグランディンの合成が阻害されてプロスタグランディンが無くなると、胎児の動脈管が収縮し、右心室から出た血液が動脈管へ流れる量が減り、未だ呼吸をしていない肺へ流れて負担がかかるようになる。すると肺動脈の血管抵抗が高まり、さらに右心室に負担がかかることで、右心室圧が上昇し、出生後も持続して遷延性肺高血圧となる可能性がある。
3) 咳のひどいとき•喘息
≪妊婦が咳および喘息のひどいときはどんな危険があるか≫
•激しい咳の持続は、子宮収縮を起こし、切迫早産の原因にもなりかねない。
•喘息発作で、母体が過換気になり、低炭酸ガス血症になると子宮動脈の収縮が起こり、 胎児に危険が及ぶ。
•母体が低酸素血症になっても危険であり、このような変化自体が胎児の生命に危険をもたらす 。
≪妊婦が咳止め内服薬を飲んだが大丈夫か? ≫
•「デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物」は、限られたデータではあるが妊娠中での安全性が報告されている。
(→多くの産婦人科医が使用しており使用可能と思われるが、漫然とした投与は避けることが望ましい。)
≪妊婦の喘息に使いやすい薬はなにか? ≫
・抗アレルギー薬の「クロモグリク酸ナトリウム」は、催奇形性は動物でもヒトでも報告されていない 。
また吸入剤として利用することで母体血中濃度が上昇しないため、妊娠中の女性に使いやすい。
•気管支拡張薬では、「サルブタモール硫酸塩」が最も使いやすいとされている。吸入においては、催奇形性は報告されていない 。
☆喘息の場合は、特に薬物療法によって喘息発作を防止することが非常に重要で吸入ステロイド剤を使いしっかりコントロールする必要がある。
○肺炎・抗生剤の必要な病気
≪ 肺炎の予防・治療に使用される薬はなにか?≫
•「ペニシリン系」や「セフェム系」の抗生物質を感受性を確認しながら利用する。
○インフルエンザ
≪妊婦にインフルエンザワクチンは接種してよいか?≫
•「インフルエンザワクチン」は 不活化ワクチンであり、安全と考えられている。
≪インフルエンザにかかった時はどの薬物を使用するか ≫
•抗インフルエンザ薬の「ザナミビル水和物(リレンザ)」は吸入であるため、使用は可能である。
•「ペラミビル水和物(ラピアクタ注射液)」については、妊娠期に 関する使用情報はまだ少ない。
○下痢のひどい時
≪ 水様性便などのときは薬を飲ますのか≫
・下痢止めとしては、「ロペラミド塩酸塩」が利用できる。ヒトでの催奇形性の報告はない。
○便秘のとき
≪ 妊娠により便秘はひどくなるか?≫
・妊娠中は、食事内容の変化や運動量の低下、子宮の増大による腸管の圧迫などのため便秘を起こしやすい。
・黄体ホルモン優位の状態となるため、自律神経系が交感神経優位となり、さらに便秘を加速する 。
≪ 便秘のとき薬は使うべきか?≫
・基本的には、薬物を使わずに、食事療法が第一選択となる。食物繊維の多い食品を取るように指導する。適度な運動や十分な水分補給も大切である
・どうしても使用する場合は、一時的、補助的なものとして、「マグネシウム塩類下剤」や「パントテン酸」を使用。
・それでも効果がない場合は、大腸刺激性下剤の「ピコスルファートナトリウム水和物」や「センナ」、「センノシド」、「ビサコジル」などが使用される
≪ 妊婦は便秘の時に漢方薬、健康食品はつかってよいか?≫
・漢方薬でも大黄、ボウショウ、ケンゴシを含む漢方製剤は、流産を誘発する危険性があるため使用しない
・基本的には、「桂枝加芍薬湯」、「小建中湯」などが利用されている
・健康食品の「アロエ」は、その成分が胎盤を通過して胎児の腸管を刺激し、羊水中への胎便の排出を促すことがあるので、妊娠中は避ける
≪ 妊婦が便秘時になりやすい病気はなにか?また、その対処法は?≫
・便秘に加えて、直腸や肛門のまわりの静脈が うっ血して痔にもなりやすくなる。
・また、痔の薬の多くは軟膏や坐剤で、局所投与で頓用なので胎児への影響は少ないと考えられる。しかし、ステロイド剤が含有されているので、長期連用は避ける。
○ 花粉症
≪妊娠性鼻炎とはなにか?≫
・妊娠中の女性は、鼻づまりが悪化しやすくなる。
※妊娠時には、女性ホルモンの分泌が増加して、循環血液や体内貯留水分の量が増加する。毛細血管抵抗の減少もあって、血管壁が拡張し、鼻粘膜の充血や腫れが起こってくる。
≪薬物療法の前にしておくことはなにか?≫
・ 花粉症の場合は、マスクやめがねを利用して、抗原である花粉に接しないようにすることも重要である。
≪花粉症・鼻炎で妊婦にまず使用すべき薬剤、使える薬剤 ≫
・薬物療法を選択する場合は、まず、「クロモグリク酸ナトリウム」や「抗ヒスタミン薬」などの点鼻薬を選択。
・ステロイド剤でも点鼻製剤は、利用しやすい。第二世代の抗ヒスタミン薬では、「ロラタジン(クレリチン)」や「セチリジン塩酸塩(ジルテック)」、「フェキソフェナジン塩酸塩(アレグラ)」などが、催奇形性は否定的である。
≪妊娠中注意すべき鼻炎の薬はなにか?≫
・市販薬にも含まれている「ナファゾリン塩酸塩」や「テトラヒドロゾリン塩酸塩」などの血管収縮薬は、子宮収縮の作用も持つため、注意が必要である。
○ 睡眠薬
≪ 妊婦の不眠にまずすべきことはなにか?≫
・妊娠中の女性の不眠には、一般的には散歩や妊娠体操などの適度な運動やぬるめのお風呂などが勧められる。
・しかし、不眠が続き、安静が保たれず、母体や胎児への影響が考えられる場合には、睡眠薬が投与されることがある。
≪妊婦の不眠に使用されている薬はなにか?≫
・漢方薬では柴胡加竜骨牡蠣湯、抑肝散、加味逍遥散などが、妊娠中の女性の証に併せて選択されることがある。
・ベンゾジアゼピン系の薬物については、催奇形性が増大する結果は認められていない。
(一時的な使用では、危険性の増大は大きくないと考えられている。しかし、妊娠後期に連続して服用すると、新生児薬物離脱症候群が発生し、一過性の傾眠や呼吸器機能への影響が起こる可能性があることを念頭に置く必要がある。)
○ステロイド外用薬
≪ステロイドの塗り薬は安全か≫
・“一般的な使用量、使用方法であれば”外用したステロイドの経皮吸収の量は少なく、妊娠中でも特に問題はない。
○膣カンジタ・水虫治療薬
≪妊娠期での真菌治療はどうすればよいか?≫
・妊娠期には、高濃度のエストロゲンにより膣上皮細胞内のグリコーゲン濃度が上昇することなどから、膣カンジダ発症しやすい。
・「クロトリマゾール」などは、膣カンジダ症に使用しても胎児への影響は報告されていない。
≪水虫の塗り薬は使ってよいか≫
・水虫の場合も、一般的な外用の抗真菌薬であれば、血中濃度は内用薬に比べて 1/10 程度と考えられており、問題はないと考えられる。出産後でも可能なものは、積極的な治療の対象とはならない。
○甲状腺亢進症・バセドウ病治療薬
≪ 薬物治療の継続はどうすればよいか ≫
・母体の甲状腺機能亢進症は妊娠経過に悪影響を与えますから、バセドウ病で甲状腺ホルモンが多い時は治療しなくてはいけません
・一般的には抗甲状腺剤によって奇形の頻度が増すとの証拠はありません。治療しないでホルモンが多いままにしておく方が害が大きいと考えられています。
・バセドウ病治療薬(抗甲状腺剤)には「チアマゾール(メルカゾール)」、「プロピルチオウラシル(チウラジール、プロパジール)」の2種類がありますが、妊娠中、授乳中は「プロピルチオウラシル」の方が望ましい。
○糖尿病
≪ 妊娠中の血糖値が高いとどのような問題がおきるか?≫
お母さんが高血糖であると、赤ちゃんも高血糖になり、いろんな障害が起こる。
・お母さん:妊娠高血圧症候群、羊水量の異常、肩甲難産など
・赤ちゃん:流産、奇形、巨大児、心臓の肥大、低血糖、多血症、電解質異常、黄疸、胎児死亡など
≪ 妊娠中の糖尿病薬にはなにが使われる ≫
・「インスリン製剤」は分子量が大きく、胎盤を通過して胎児に移行しないため、妊娠中の治療に用いられる。「経口血糖降下薬」で治療をしていて妊娠を希望される場合には、妊娠前にインスリン療法に変更する。
・妊娠中は妊娠時期によってインスリンの効き方が異なる。妊娠初期にはインスリンは効きやすくなり(インスリン感受性)、妊娠中期以降にはインスリンは効きにくくなり(インスリン抵抗性)、血糖値が上昇しやすくなります。よい血糖コントロールを達成するために、食事療法のみで治療をしていた妊婦さんでも妊娠中期以降にインスリンを開始し、妊娠前からインスリン療法を行っていた妊婦さんではインスリン使用量を増やします。
○ タバコ
≪ たばこの胎児へどのような影響をあたえるか≫
・タバコの煙にはニコチン、一酸化炭素、シアン化合物、鉛などが含まれている。これらの成分は、血管収縮作用があるため、胎児への酸素供給を阻害する。特に、子宮内胎 児発育遅延は喫煙本数に関係し、一般に母親が喫煙していると出生時体重は約 200g 軽 くなるといわれている。
≪ 妊婦の喫煙でどのような病気がおこるか ≫
・流産、早産、前置胎盤、胎盤早期剥離などの異常も非喫煙者の 2〜3 倍になる。早産率は、1 日 5 本以上で 7%、1 日 20 本以上で 25%増加するといわれ ている。
≪ 夫や家族の喫煙は妊婦にどの程度の影響をあたえるか?≫
受動喫煙も一般には 1 日 1~5 本程度の喫煙と同じ影響があるといわれているので、パートナーの喫煙も控えるように、もしくは妊娠中の女性が受動喫煙を受けないように配慮するよう指導する。
○ アルコール
≪ 妊娠中の飲酒は胎児にどのような影響をあたえるか?≫
・絶対過敏期にアルコールに暴露されると、奇形が起こり、妊娠後期では、発育異常や 中枢神経系障害が起こる
・妊娠中の飲酒による胎児への影響は、胎児性アルコール症候群(Fetal alcoholsyndrome:FAS)と呼ばれている。
※妊娠中にアルコールを摂取した女性から生 まれた子供にみられる症状を総称したもので、特徴的な顔貌(小さな目、薄い唇など) や、発育の遅れ、中枢神経系の障害(学習、記憶、注意力の持続、コミュニケーション、 視覚・聴覚の障害など)などがある。また、中枢神経障害が主体で、上記のような特徴は、アルコールとその代謝産物のアルデヒドが、胎盤を通過し、胎児細胞の増殖や発達 を障害するためと考えられている。
≪ アルコールはどれぐらい量が危険か?≫
・一日アルコール摂取量が 15mL 未満、すなわちビール 350mL 缶一本程度であれば、胎児への影響は少ないと考えられている。しかし、90mL 以上、 すなわち、ビール大瓶 3 本程度になると、明らかに奇形の発生が高くなる。
・毎日飲酒しなくても大量を時々飲むことでも胎児性アルコール症候群が発生することが 知られている。特に、中枢神経系障害の発生はアルコール摂取量 70~80mL、つまり、 ビール 350mL 缶 5 本程度を週に数回飲んでいた母親に多く発生している
12.奇形防止と葉酸
≪ 葉酸にはどうよう効果があるか ≫
・葉酸は、DNA を構 成している核酸やタンパク質の合成を促進する働きを持つため、これが不足すると胎児に 神経管閉鎖障害が起こりやすくなるといわれている。平成13年からは、母子手帳にも葉酸 の摂取についての記事が記載され、二分脊椎などの神経管閉鎖障害の防止に対して、葉酸をはじめビタミンなどを多く含む栄養のバランスのとれた食事の必要性を推奨している。
≪ 葉酸を栄養補助食品で補うことは可能か≫
・妊娠可能な女性の 葉酸摂取率は、いまだに低く、葉酸は水溶性ビタミンであり、食品からの利用効率に差があるため、栄養補助食品で補うことも必要となる。
【 授乳のときの薬剤 】
1;授乳に関する基本的な考えかた。
Q;授乳を中止した時のデメリットはなにか?
A風邪をひいているお母さんの母乳には、その風邪のウイルスに対する免疫がたくさん含まれており、赤ちゃんが風邪にかかるのを予防したり、かかっても軽くしたりする働きがあります。母乳から風邪がうつることはありませんし、人工乳に代えてしまえば、赤ちゃんは免疫を得られなくなります。
・急に授乳をやめてしまうと、お母さんが乳腺炎などの乳房トラブルを起こしやすくなります。一時的にせよ授乳をやめると、母乳の出が悪くなることもあります。
Q;母乳に出るお薬で赤ちゃんに影響はでるか?
A:。赤ちゃん自身が風邪にかかったときに小児科で処方される薬の量に比べて、母乳に出る薬の量は非常に少なく、赤ちゃんに影響が出る可能性は非常に低いと考えられる。
2: 解熱鎮痛薬・局所麻酔薬
Q 歯痛や頭痛で痛み止め(ノーシン・イブ)を飲んでしまったが、大丈夫か?
A:イブプロフェン(医療用ブルフェン他)は痛みや腫れを抑える効果が強く、母乳中にはわずかにしか出ないので、いちばんお勧めだとされています。
Q 腰痛で飲み薬が出たが、心配なのでミルクにしようか断乳しようか考えている。
A;鎮痛効果の強いジクロフェナクナトリウム(ボルタレン)は、血液の中のタンパク質との結びつきが強く、薬の性質として母乳の中に非常に出にくいので、痛みが激しいときに使うことができます。
Q 歯科治療で麻酔を使って大丈夫か?
A: 歯科治療のための局所麻酔薬は血液の中には入りませんから母乳の中にも出ず、授乳に
は差し支えありません。また、効いている時間も短いので、授乳を控える必要はありませ
ん。
3:予防接種
Q 麻疹・風疹の予防接種を受けたが授乳してよいか?接種後いつからなら良いか?
A :麻疹・風疹を含めすべての予防接種は授乳中に接種できますし、やめる必要はありません。接種後すぐに授乳してかまいません。
・生ワクチンは妊娠中には受けることができませんので、お母さんが麻疹や風疹にかかったかどうか、はっきりしないときは、出産後すぐに(できれば産婦人科入院中に、それが難しい場合は産後1か月以内に)ワクチンを受けるようにしましょう。
Q インフルエンザの予防接種をしたが、授乳してもよいか?
A:インフルエンザワクチンは不活化ワクチンであり、生きたウイルスは含まれていないので、母乳中にウイルスが出ることはなく、授乳中の赤ちゃんに影響があるとは考えられません。妊娠中・授乳中のインフルエンザワクチンにより、お母さんからの免疫が胎盤や母乳を経由して赤ちゃんに移行し、赤ちゃんのインフルエンザを軽くする効果があることがわかってます。
Q インフルエンザに罹り、(リレンザ・タミフル)が処方され使ってしまった。母乳を飲ませてよいか?
A; オセルタミビルリン酸塩は母乳の中に出る量が非常に少なく、母乳を通して赤ちゃんに影響が出る可能性はほとんどありません。患者さんが心配なときは、吸入のザナミビル水和物(リレンザ)を使います。
最近新しく承認されたペラミビル水和物(ラピアクタ)、ラニナミビルオクタン酸エステル水和物(イナビル)は子どもにも使われることがありますし、吸入や注射で使う薬なので、母乳に出ないか、出たとしても赤ちゃんの胃や腸から吸収されにくい薬ですので、心配ありません。
・高熱などの症状がつらいときは、解熱鎮痛薬(授乳中はイブプロフェンが勧められています)を使って症状を和らげることができます。
Q;インフルエンザにかかったら母乳はしないほうがよいですか?
A;インフルエンザウイルスは母乳へは出ませんので、母乳からインフルエンザが赤ちゃんにうつることはありません。お母さんだけでなく、家族がインフルエンザにかかったら赤ちゃんにうつる可能性があ
るのは、母乳栄養でも人工栄養でも同じことです。母乳には免疫がたくさん入っていますから、赤ちゃんがかかったとしても症状を軽くすると言われています。
抗アレルギー薬
Q:授乳中にアレルギー薬は飲んで大丈夫か?
A: 抗アレルギー薬は母乳に出にくい薬が多く、母乳を通して赤ちゃんの体内に入る薬はわ
ずかであり、赤ちゃんに影響が出ることはまずありません。しかし、お母さんが強い眠気を催す薬は避けた方がいいでしょう。また、心配なら乳児にも使う薬を出してもらうといいかもしれません。
その中でも、ペミラストロカリウム(ペミラストン・アレギサール)、フェキソフェナジ
ン塩酸塩(アレグラ)、ロラタジン(クラリチン)は母乳へ出にくく、眠気も少なくて、授
乳中の人には向いています。
Q :授乳中、アレルギー性鼻炎でステロイド点鼻は使用可能か?
A:ステロイド点鼻薬が副作用も少なく、お母さんの血液にもほとんど入りませんので、安全に使うことができます。
Q アトピーの症状が悪化、薬を飲み断乳するほうがいいか、薬を飲まないほうがいいか?
A:アトピーの治療は塗り薬が中心になるでしょう。ステロイド外用薬は、皮膚から吸収されて血液の中に入るとしてもごくわずかで、それが母乳の中へ出るほどの量になることはまずありません。
Q 花粉症で予防的治療(皮内注射)したら、乳児への移行はどうなのか?
A :花粉症予防の皮内注射には数種類ありますが、特異的減感作療法にしても、人免疫グロ
ブリン・ヒスタミン二塩酸塩(ヒスタグロビン)にしても、分子量が大きく母乳中へ出るとは考えられません。従って、母乳を通しての赤ちゃんへの影響は心配いりません。
睡眠薬・抗不安薬
Q デパス0.5mg を飲んだら、次の授乳までどれくらい空けたらよいのか?
A エチゾラム(デパス)をエチゾラムは血液中のタンパク質へ結合する割合が高く(蛋
白結合率93%)、母乳中へは出にくい薬ですので、通常通り授乳して差し支えありません。
※2mg の錠剤を1錠飲んだ場合、血液中の薬の濃度が最大に達するのが、服用後約3.3 時間
(Tmax=3.3±0.3)、半分に減るのが約6.3 時間(T1/2=6.3±0.8)です。血液中の薬の濃度は最
大になったときでも、とても低く(Cmax=25±1.5ng/mL)、母乳に出る量はそれよりはるかに
少ないので、実際には赤ちゃんへの影響はほとんどないと考えられます。
実際にデパスを飲んだお母さんの母乳の中の濃度を測定してみたところ、検出されなか
ったという研究もあります。
その他
Q:子宮収縮剤1 週間服用、医師・薬剤師とも母乳は大丈夫と言ったが心配になった。
A;母乳と薬のことが載っているデータ・ブックによると、子宮収縮剤が母乳に出る量はご
くわずかで、1週間程度の内服であれば、明らかな問題は起こりにくいだろうと書いてあ
ります。頻繁に授乳することは、オキシトシンというホルモンの働きで子宮を収縮させることを
促すことにもなりますので、お母さんの産後の回復のためにも授乳をすることは役に立ち
ます。
外用薬
Q 腰痛でシップ剤を貼ってよいか?
緑内障で目薬を使っているが、授乳してよいか?
Q 便が硬く切れ痔になったが、ステロイドの入った坐薬をつかってよいか?
A 貼り薬や目薬、軟膏などの外用薬を使用した場合も、授乳は大丈夫なのか気になっておられるのですね。
その場所でしか効果のない薬は、血液の中にほとんど入りませんので、母乳の中に出ることもほぼありません。母乳は血液から作られますので、血液の中に入らない薬は母乳にも出ないのです。
がって、湿布薬、軟膏、点眼薬、点鼻薬など、その場所だけで効果を示す薬は、どれも授乳には差し支えないと考えられます。
喫煙
Q ストレスで1 日1〜3 本タバコを吸っている。子供への影響が心配。
A :母乳の中には人工乳には含まれていない免疫や生きた成分などがたくさん入っているので、たとえお母さんがタバコを吸っていても、母乳をあげることのメリットの方が大きいと言われています。(母乳の中にはニコチンなどタバコの中の有害成分がわずかではありますが出ます。)
・しかし、母乳を飲ませなくても受動喫煙をする条件は同じで、受動喫煙による害の方が、母乳中のニコチンなどによる害よりもはるかに大きいのです(母乳からのニコチンより17倍多いというデータがあります)。・たとえすぐに禁煙できなくても、受動喫煙を避けつつ、授乳は今までどおり続けましょう。
飲酒
Q 飲酒した場合、どれくらい母乳を与えないほうがよいか?
A :アルコールは胃からの吸収がよく、すぐに血液から母乳にも入ります。しかし、肝臓で処理される速度も速く、すぐに血液からなくなってしまいます。お母さんが「酔いが醒めた」と感じたら、血液の中のアルコールも減ってきたということですので、授乳をしてかまいません。